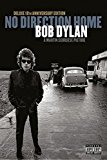
ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞を本当に嬉しく思う。高2で出会ったディランは、僕の人生を変えた。僕が音楽評論家になったのは、ディランの影響に他ならない。
アルバム『BLOND ON BLOND』(1966年リリース)を何度聴いたことだろう。難解な歌詞は、いまだに読み解けずにいる。表面的な翻訳は何度もしたが、かえって訳がわからなくなるだけだった。それよりも、ディランの歌に身を浸している方がいい。確実に何かが伝わってくる。言葉はディランの歌の一部に過ぎず、しかし僕は文学的感動を受け取ってきた。
今も評論をしていて難解な歌詞に出会うと、その経験を思い出して、無理に言葉の解釈をせずに、音楽に身を浸すようにしている。そこで感じることの方が雄弁だからだ。僕の音楽評論には、ディランの作品が色濃く反映されている。
その後、僕は俳句を始めたが、俳句について深く考えるようになってから、俳句とディランの関係に気付いた。僕が俳句に魅かれたのも、きっとディランの影響に他ならない。
僕は10年ほど前、俳句とディランについて書いたことがある。僕は俳句結社誌『鴻』に、“ON THE STREET”というコラムを連載している。2007年2月号に寄せたその原稿に、若干、手を入れて、ここにアップしたいと思う。
題材はマーティン・スコセッシが監督した若きディランのドキュメント映画『ノー・ディレクション・ホーム』(2005年 公開)で、原稿のタイトルは「遠<旅する者たちへ」とした。
「遠<旅する者たちへ」
ボブ・ディランは1960年代に「風に吹かれて」という歌を大ヒットさせたアメリカの歌手で、ご存知の方も多いだろう。日本でもディランの真似をして、反戦歌ブームやアングラ・フォーク運動が起こったりした。その影響力は絶大で、ある意味、ビートルズと肩を並べるほどだった。現在でも井上陽水や桑田佳祐が彼に大きな影響を受けていることを言明している。
ボブ・ディランは歌と社会、歌と時代の関係に新しい局面を切り開いた。今回、紹介するDVD『ノー・ディレクション・ホーム』はディランの優れたドキュメント作品で、アメリカ合衆国の激動の60年代の本質に真っ直ぐに迫っていて興味深い。
移民としてアメリカにやって来た人々は、それぞれの土地でフォークソング=民謡を作り、歌い、過酷な生活の慰めとして来た。が、20世紀半ばに生活が豊かになるに連れてフォークは衰退していった。
60年代にフォークが復興するきっかけとなったのは、人種差別やベトナム戦争といった社会的ストレスから解放されることを望む人々が、古典的なフォークの良さを再発見したからだった。その最先鋒がボブ・ディランだったのである。
注目したいのは、アメリカのフォークソングのほとんどが“ホーボー”と呼ばれる流浪の民の叙事詩であることだ。ホーボーは収穫期にだけ雇われる最下層の農業労働者階級で、鉄道の切符さえ買えない貧しさから、列車の屋根に乗って移動したりしていた。その様子は、映画『天国の日々』などに描かれている。
ホーボーたちのフォ―クソングは、伝記的叙事詩の側面が強かった。どこで誰が何をしたのかなど、“無名の人々”の人生の記録だった。それが人々の慰めになったのは、広大な大地でちっぽけな人間が生きたことの証しを立てることの難しさを表わしてもいる。
豊かになる一方で、大きく歪み始めた社会の中で、再び人々は“無名化”して戦争に駆り出され、悩みや不安から、かつてのフォークソングに救いを求めたのだった。
ディランはレコードを一、二度聴いただけですぐその歌を億えてしまう特技の持ち主で、少年期に恐ろしい量のフォークソング=叙事詩を吸収蓄積した。叙事詩はバラード、バラッドとも言い、初期のディランはこうしたアメリカのバラッドを主なレバートリーとしていた。
その後、彼はフォークソングにエレキギターやドラムなどを導入して“フォークロック”というジャンルを創出する。その“フォークロック”の代表作が「ライク・ア・ローリング・ストーン(転がる石のように)」という曲で、このDVDはフォークの「風に吹かれて」から、ロックの「ライク・ア・ローリング・ストーン」までの初期のディランの姿を克明に写し取っている。
このDVDで衝撃的なのは、60年代アメリカの一大エポックであった「ワシントン平和大行進」の際、ディランが演説用のマイクで弾き語りをするシーンだ。極度に削ぎ落とされた言葉で、民衆の立場から戦争の愚かさを大群衆にとつとつと伝える。その冴えた手腕は、フォークなど知らなかった人々を驚かせ、熱狂させた。
しかし伝統的なフォーク・ファンからは、あまりにも時事的なディランの歌作りに疑問の声が上がった。それに対して、ディランは記者会見で自分の反戦フォークについてこう語っている。
「フォークには、古い歌を作り替えて、新しい歌として歌う手法が昔からあった。僕はそれにのっとって曲作りをしているだけ。僕が初めてではないし、画期的でもない」。
ディランはかつてのフォークソングがそうであったように、その時代その時代の生の感情を歌おうとした。彼にとってフォークは伝統芸能ではなく、今を生きる歌だったのだ。
またディランは、歌に登場する事象、たとえば「激しい雨」などの言葉を「原爆の黒い雨」の比喩と受け取りたがる反戦気取りのエセ知識人達の憶測をきっぱりと否定する。ディランにとって“激しい雨”はそれ以上でもそれ以下でもない。聴いた人間が“激しい雨”という言葉をどう解釈するのかは自由だが、自分はただ“激しい雨”という事象を歌っているだけだとディランは言う。それはバラッド=叙事詩をとことん突き詰めた人間にしか分からない、言葉に対する敬意の表れだった。
この言葉に対する敬意、あるいは矜持は、俳句でしばしば言われる「具象性」や「写生」に通じている。私達は俳句で物以上の物は描けないし、“比喩としての言葉”は限りある17文字の俳句においては無駄でしかない。俳句は叙事詩というには短か過ぎるという反論があるかもしれない。だが、「花冷えの田より抜きたる足二本 本宮哲郎」(季語・花冷え 春 桜の咲く時期に急に気温が下がること)などの句を見れば明らかだ。この句には、農村のリアリズムがあふれている。
短歌が叙情詩の特質を持っているなら、俳句の本質はやはり叙事詩だと言わねばならない。叙事詩であるからこそ17文字の制限が有効で、そこに俳句の面白さや深さの生まれる余地がある。
やがてディランはより現代的で差し迫った問題を歌うべく、強力なリズムを持つロックに接近していく。彼の創出したフォークロックのテーマは、現代の「故郷喪失」。迷走する時代のバラッドを追求していく。
そんなディランの創作現場に迫る、貴重な映像がこのDVDに収められている。彼がロンドンに降り立って、林立する広告看板から“詩”を読み取っていくシーンがとても面白い。
「求む/タバコを売る店」
「求む/犬をシャンプーして送り届けてくれる店」
「求む/手数料で動物や小鳥の売買をする店」
などの看板を前に、ディランは即興で詩を組み立てる。
「風呂を洗い、タバコを届けてくれる人/大募集」
「動物にタバコを/小鳥に手数料を」
と次々に読み替えていく。
現代詩にはこうもり傘とミシンを出会わせることで、読み手を驚かせたり混乱させたりする手法があるが、ディランはそれを頭の中の作業としてではなく、現実の看板の前でやってのける。それは彼が徹底的にバラッド=叙事詩にこだわってきたからこそ行き着いた境地なのだと思う。迷走を迷走のまま、混乱を混乱のまま、バラッドに仕立て上げる方法をまざまざと見せつけられた気がして、この読み替えが50年も前に行なわれたこととは思えず、深く感動してしまった。
俳句にもこうした“物のぶつかり合い”の句がある。
「月いづこ鐘はしづみて海の底 松尾芭蕉」(季語・月 秋)
江戸時代の俳句としては、超モダンな響きがある。「月」も「鐘」も見えないのに、この二つの物が“海の底”で出会っているのである。こうした描写は、ディランにもある。♪誰も痛みを感じない。今夜、俺は雨の中に立っている♪(「Just Like a Woman」より)は、芭蕉が描いた“不在の感覚”に非常に近い。
「渡り鳥見えますとメニュー渡さるる 今井聖」(季語・渡り鳥 秋)
大きな湖のそばのレストランでの句だろうか。渡り鳥とメニューの出会いが、意外でもあり、自然でもある。解釈はすべて読み手に委ねられ、句の中には結論も説明もない。“意外”と“自然”が同居しているのは、ディランの「動物にタバコを/小鳥に手数料を」
の手法に似ている。それこそ「渡り鳥にメニューを」と読み替えたくなる一句だ。
俳人は、俳句を“文学”とは言わない。“文芸”と呼ぶ。それは俳句を卑下しているのではない。“学”というほど偉そうなものではなく、あくまで日々の生活の“お楽しみ”の詩だから、“芸”と呼ぶのである。今回、ディランはポップ・ミュージックとして初めてノーベル文学賞を受賞した。それについては異論のある人もいるようだが、だとしたら“ノーベル文芸賞”でもいいと思う。ディランも俳句と同じく、同時代の不安な人々をいっとき慰めるために歌を作り、歌っているのだと僕は思う。
ちなみにタイトルの「ノ―・ディレクション・ホーム」は、「帰り道はない」というほどの意味である。その覚悟で新しい道を切り拓き、歌い続けてきたディランの心意気を感じる。
「旅に病んで銀河に溺死することも 寺山修司」(季語・銀河 秋)





















