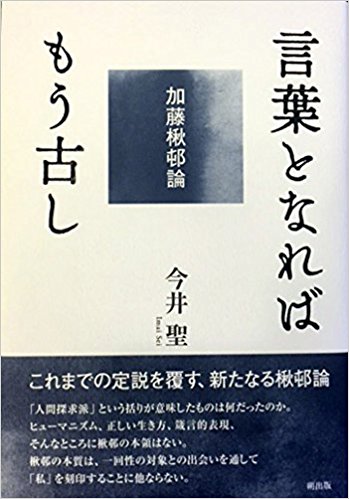
『言葉となればもう古し-加藤楸邨論-』 今井聖・著 朔出版・刊
今年の俳人協会評論賞受賞作である。俳句結社『街』主宰の今井聖氏が、師である楸邨について論じた一冊で、楸邨俳句の基点から始まって、『寒雷』や『雪後の天』など刊行された全句集を詳細に解説している。これまで結社誌『街』や『馬酔木』、俳句総合誌『俳句研究』などに発表されてきた楸邨に関する文章を加筆修正してまとめたもので、長年にわたる聖氏の楸邨研究の集大成となっている。俳壇の内外に常に問題意識を持ち、議論をいとわず己の俳句を研鑽していった楸邨を分析していく過程は、そのまま聖氏の俳句の拠り所を示していて、楸邨論でありながら、俳人・今井聖のマニフェストの様相を呈している点が非常に興味深い。
楸邨は「人間探求派」と呼ばれるのが通例になっている。しかし、山本健吉によって付けられたその呼称は本質を正しく捉えてはおらず、言葉からイメージされる「ヒューマニズム」や「箴言」といったものとは異なる次元で楸邨の俳句作りは行なわれていたと、この本は繰り返し述べる。聖氏はこのテーマを主軸に、角度を変えて何度も評論を試みていて、それらがまとめられることによって立体的な楸邨像が浮かび上がってくる。そこが本書の要だろう。「人間探求派」という定説に挑戦するために、著者はユニークな視点をいくつも用意して論陣を張る。
まず、字余りの多い楸邨俳句の根拠となった「十七音量性」から説き始める。これは、「十七音」の「量」の問題を意味する。たとえばその句が十九音や十五音であっても、ラップのように詰め込んだり引き伸ばしたりして、「十七音の量」で発音できればよしとするのである。「羅漢みな秋日失せゆく目が凄惨」(季語:秋日 秋)、「遺壁の寒さ腕失せ首失せなほ天使」(季語:寒さ 冬)など破調の例句を的確に選ぶ聖氏の眼の鋭さは、師・楸邨への愛情と敬意に裏打ちされている。
有名な「しづかなる力満ちゆき螇蚸とぶ」(季語:螇蚸 秋)の句には、「勇気を与えてくれる」だとか「忍耐が大事」などと寓意を持ち出す鑑賞者が多い。だが聖氏は、「その解釈は『人間探求』という先入観にとらわれて楸邨の特質を見ていない」ときっぱり否定する。その上で“螇蚸”は“バッタ”ではなく、“はたはた”と読み、楸邨は意図的に字余りにすることでリアリティを獲得しようとしたと、きちんと証拠を示して断言する。
一方で、高濱虚子など他の重要な俳人についても、思い切った持論を展開。虚子のスローガンである“花鳥諷詠”を、「誰もが共有し得る先入観や通念に自分を寄せていく。そのことに抵抗を感じなくなる齢に見合った美意識と言い換えてもよいかもしれない」と厳しく規定し、正岡子規の唱えた本来の“写生”との違いを明らかにする。
また昭和の俳壇に一大論争を巻き起こした桑原武夫の『第二芸術―現代俳句について』も要旨を簡略に示し、70年以上を経た現代にも通じる俳人の保守傾向や結社の意義の曖昧さを指摘。ただ、そうした慧眼を持つ桑原でさえ、子規の出現の意味を理解していなかったと聖氏は述べる。
その明快な論調は、胸が空くようで小気味がいい。氏の俳句講座を受けたことのある方はすぐに思い当たると思うが、快刀乱麻とはこのことだ。そして子規の業績を、「リアルの系譜―子規から楸邨へ」の章でさらに深く探っていく。
無季の句では「非常口に緑の男いつも逃げ 田川飛旅子」を例に挙げ、季節感を表わさない「緑」は夏の季語とはならないが、現代社会を生きる人々の持つ不安や危機感を“客観写生”の方法で見事に切り取っていると評する。その流れの中で「銀行員等朝より蛍光す烏賊(いか)のごとく 金子兜太」の意義は、農工業ではなく、第三次産業の労働を詠んだところにあると喝破。このあたりから本書は佳境に入る。
「髪も紅も突つ込む蕎麦の湯気の中 秦鈴絵」や「太刀魚の立ち泳ぐさま傘で言ふ 加藤精一」(季語:太刀魚 秋)などの美容師や板前の詠んだ労働俳句を挙げて、楸邨が志したのは労働賛歌やヒューマニズムではなく、ひたすら現場のリアルだったのではないか、彼らが身体を通して感じた即時的なポエジーだったのではないかと結論する。
面白かったのは、楸邨の結社『寒雷』で若手が造反したときのエピソードだった。不満を持った兜太や沢木欣一らの中の一人が、主宰に「自分たちに選句をさせて欲しい」と詰め寄ると、楸邨は一言の元にそれを断る。断ったのは当然のこととしても、今では信じられないような文学的緊張感のある師と弟子の関係が、60年以上前にあったのだと聖氏は憧憬を込めて振り返る。
僕はこのエピソードを読んでいて、聖氏にもこの血が流れていて、師・楸邨の残した作品と真っ向から切り結ぶ覚悟が引き継がれていることを直感した。そのことが『言葉となればもう古し』を、生な実感のこもった評論集として成り立たせているのだ。そしてこの鋭利な論調は、今を生きる俳人の抱える問題にも、遠慮なく及んでいく。もちろん聖氏も自戒を込めて、自身の俳句に向かう姿勢を検証する。このフェアさが、本書の最大の良さだ。
今井聖は俳句の力を信じてこの本を著した。この快作が受賞を果たしたことは、今後の俳壇に大きな意味を持つだろう。僕らもその俳壇の中にいる。
「転校生蛇が摑めてすぐ馴染む 聖」(季語:蛇 夏)
俳句結社誌『鴻』2018年3月号より転載





















